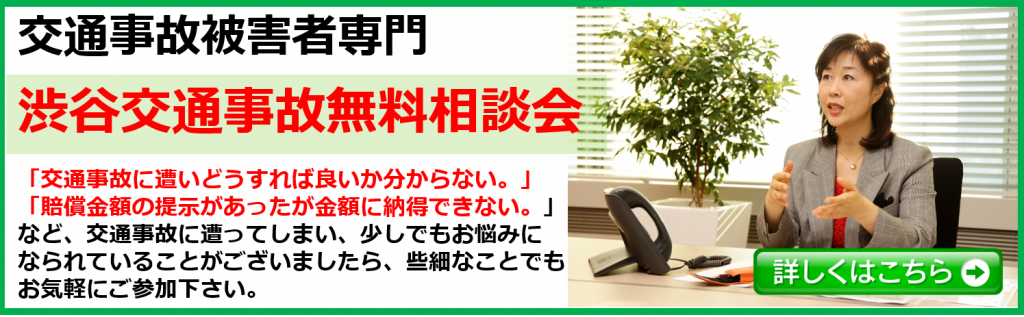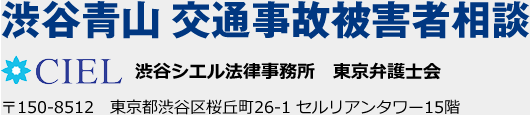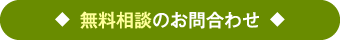【高齢者の交通事故判例⑬】84歳男性が自転車走行中、自動車と出会い頭衝突をし、自賠責保険後遺障害等級1級に相当する後遺障害が残存したと主張して1200万円の支払を求めた裁判で、91万円余りの支払が認められた事例
(令和2年1月17日神戸地裁判決/出典:自保ジャーナル2073号21頁等)
事故状況
84歳男性が、自転車で歩行者用信号機の青色表示に従って横断歩道を横断中、赤信号で交差点を直進してきた自家用普通貨物自動車に衝突された。
傷害(怪我)
外傷性くも膜下出血、脳挫傷、急性硬膜下血腫等
被害者の主張
事故後、入通院治療を受けたが、1年2ヶ月後に、認知機能の低下、排尿障害の症状が残った結果、全く仕事に従事することが出来なくなっただけでなく、異常行動等のために家族が絶えず見守りをして介護をしなければならない状態になり,後遺障害等級1級1号に相当する後遺障害が残存した。
判決のポイント
①本件事故による後遺障害の有無(認知機能の低下)
裁判所は、概要次のように述べて、被害者の認知機能の低下は本件事故によって生じたと認めることはできないと判示しました。
「事故直後の意識障害は軽微、事故直後は画像上脳挫傷が認められたがその後は痕跡がほとんど認めらない、脳萎縮の進行や認知機能の低下の症状経過からは内因性疾患である血管性認知症ないしアルツハイマー型認知症によるものと推認される」
②本件事故による後遺障害の有無(排尿障害)
裁判所は、排尿障害についても、「本件事故以前から原告には頻尿の症状があり、排尿障害が生じていた」と述べて、本件事故によって排尿障害が生じたとすることはできないと判示しました。
小林のコメント

判決では、本件事故以前から頻尿であったことや、近医においてアルハイマー型認知症治療薬が処方されていこと、さらには認知機能が事故後8ヶ月後に著しく低下し、その1年半後に夜間の異常行動が見られるようになった経過は脳外傷による典型的な症状経過と整合しないとも指摘され、その結果、後遺障害が否定され、傷害部分の損害として91万円余り(内訳はほぼ慰謝料)が認容されるにとどまりました。
高齢者は、事故後症状が事故前からの疾患によるものか事故によるものか判別が難しいことがありますが、本件の裁判ではこの点が厳格に判断されました。
【2025年1月24日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
(平成25年 9月27日名古屋地裁判決/出典:自保ジャーナル 1911号1頁等)
事故状況
事故現場は南北道路と東西道路が交差する交差点。東西道路には横断歩道と自転車横断帯が設置されていた。加害車(普通乗用自動車)は南北道路から東西道路へ右折しようと交差点中央付近で右折待ち停止後、発進し、その際、横断歩道上で初めて被害自転車を発見し、衝突。被害者は自転車ごと転倒した。
けが(傷害)
脳挫傷,慢性硬膜下血腫,頭部挫創,右肋骨骨折,外傷性血気胸,末梢性めまい症疑い,外傷性右肩関節周囲炎など(初診時に意識障害あり)
入通院期間
事故から症状固定まで約1年9ヶ月(入院50日、通院日数64日)
後遺障害(自賠責保険の認定)
後遺障害等級2級1号(「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」に該当)
請求内容
被害者は、不法行為に基づく損害賠償として、治療費、付添看護費、将来介護費、休業損害、慰謝料など合計1億3555万6345円の支払いを求めて提訴
判決のポイント
①過失相殺の有無・割合
加害者側は、被害者にも横断中に右方向の安全を確認しなかった過失があるとして10%の過失相殺がなされるべきと主張しましたが、裁判所は、被害者が高齢者であること,横断歩道(自転車横断帯)を通行していたことなどを考慮し、過失相殺を行うのは相当でないと判示しました。
②後遺障害等級
加害者は、被害者には高次脳機能障害が残存しているが日常生活は自立しており、介護は不要で、後遺障害等級は9級が相当(労働能力喪失率でいうと35%喪失)と主張しましたが、裁判所は、 自賠責で2級1号に該当すると判断されたこと(2級の労働能力喪失率は100%)、症状固定後、身体機能は回復したが、記憶障害や感情コントロール低下等の症状が残存しており、日常生活で声かけ等の介助が必要だとして、後遺障害等級は2級が相当であると判示しました。
③将来介護費
加害者は、被害者には将来にわたる付添や看視は必要ないと主張しましたが、裁判所は、被害者の懸命な努力により,症状固定後、自動車や自転車の運転が可能で,一人でゴルフ練習場に行けるなど日常生活動作はほぼ自立しているとしながら、記憶障害や感情コントロールの困難さが残存しているため、将来にわたり一定の介護が必要と判示しました。
もっとも、常時介護が必要な状態ではなく、日常生活における声かけや見守りなど、随時看視や見守りを要する状況であるとして、日額2000円の介護費用が相当と判断し、被害者の平均余命を考慮して、将来介護費を646万9990円と認定しました。
④休業損害
被害者は、工場経営者で自ら実働していたとして事故により21ヶ月間稼働できなくなったことを理由に休業損害として2100万円を請求しましたが、裁判所は、被害者が主張する会社の経営状況や取引に関する説明には不自然で不合理な点が多い、収入に関する的確な証拠がないといった理由により、休業損害の主張を認めませんでした。
小林のコメント

本件のように、横断歩道上を自転車で渡っていた高齢者が自動車に衝突されるケースは案外多いですが、本件のように脳挫傷等の重傷を負うケースは珍しいのではないかと思います。
また、本件では記憶障害や行動障害を伴う高次脳機能障害が残り、その程度は労働能力喪失率でいうと100%の2級相当と判断されました。
高齢者では事故前から軽度の認知障害を有している場合もあり、そのような既往の影響が考慮され賠償金が減額(素因減額)されることも珍しくありませんが、本件ではそのような減額もなく2193万円余りの後遺障害逸失利益が認定されました。
請求額との比較では認容された金額は少ないですが、妥当な判決と思います。
【2025年2月24日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか
交通事故についてもっとお知りになりたい方はこちら
| ●交通事故問題でお悩みの方へ |
●交通事故問題解決の流れ |
| ●賠償金額決定の3基準 | ●損害賠償金の計算方法 |
| ●後遺障害とは? | ●むちうち |
| ●高次脳機能障害とは? | ●解決実績 |
お気軽にお問合せ下さいませ

| ●ホーム | ●弁護士紹介 | ●事務所紹介 | ●アクセス | ●弁護士費用 |