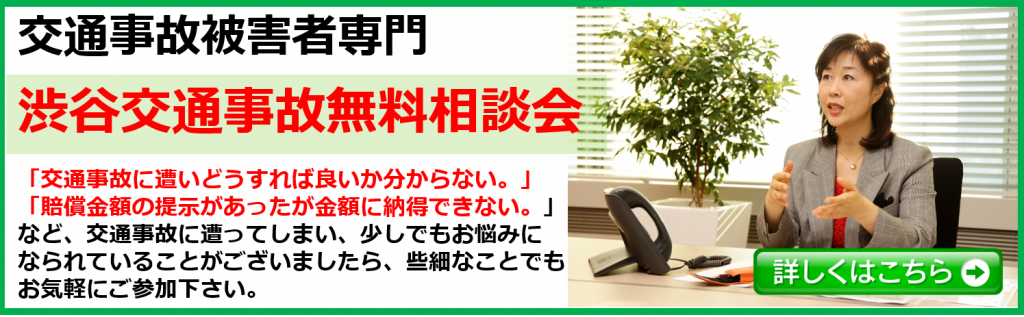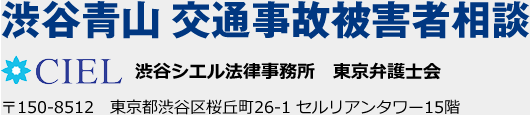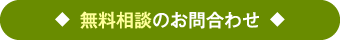【バイク事故判例㊵】バイク走行中、貨物自動車に衝突され、右肩痛および右膝痛等により後遺障害等級11級が認定された31歳の男性会社員について、逸失利益の算定において労働能力喪失期間が15年に制限された事例
(令和5年11月15日東京地裁判決/出典:自保ジャーナル№2169、33頁)
事故状況
片側2車線道路の第2車線をバイク(普通自動二輪車)で走行中、第1車線を同方向に進行していた自動車(普通貨物自動車)が右に転回して、バイクの進路を閉塞し、バイクが自動車に衝突した。
けが(傷害)
全身打撲、右大腿骨顆部骨折、右鎖骨遠位端骨折、右第1中手骨骨折、右肋骨骨折等
治療期間
入院90日、通院期間2年2ヶ月程(実日数121日)
治療経過
事故後、肋骨骨折以外の骨折に対し手術を行った。鎖骨骨折については3ヶ月~4ヶ月後に抜釘手術を、大腿骨骨折については1年9ヶ月後に内固定抜去術を受けてリハビリを行い、2年後には右拇指と鎖骨については日常生活動作において問題がなくなり作業療法を終了した。右膝については、関節痛・可能域制限および軋轢音が残り、その後も理学療法を継続し、最終的に事故から約2年2ヶ月後に症状固定した。
自賠責保険の後遺障害等級
①右鎖骨遠位端骨折後の右肩痛およびクリック音の症状につき12級3号(「局部に神経症状を残すもの」)に該当
②右大腿骨顆部骨折後の右膝歩行時痛、クリック音および右膝手術創の外側のしびれ等の症状につき12級3号(「局部に神経症状を残すもの」)に該当
以上を併合した結果、後遺障害等級は併合11級
既払額、請求額および認容額:被害者は、提訴前において相手保険会社から約995万円の支払を得ていたが、既払い金以外の賠償金として約2600万円の支払を求めて提訴。判決での認容額は約1485万円
判決のポイント
過失割合は争点となっておらず、加害車に100%の責任があることを前提に、治療費・通院交通費・付添人交通費・休業損害・慰謝料・逸失利益・将来の再手術費用などの損害全般について、その額が争われました。
例えば、被害者は治療費として個室利用費154万円程を請求し、これに対し加害者側は、個室利用の医師の指示は無く、医学的必要性(厳重隔離、隔離、免疫低下等)も認められないと反論し、個室利用費に関する裁判所の認定は、右大腿骨の観血的整復固定術等の手術を受けたことによる7日分の個室利用費に限り認める(金額は約13万円)というものでした。
このように裁判では1つ1つの損害の額が検討されましたが、以下では、最も多額な休業損害(被害者の主張は877万円)と後遺障害逸失利益(被害者の主張は1336万円)に関する裁判所の判断をご紹介します。
①休業損害
被害者は事故前、不動産仲介会社に勤務していましたが、事故後は症状固定までの809日間休業を余儀なくされ一切収入がなかったと主張しました。又、事故が無ければ同僚らと新たな不動産会社を立ち上げてより高い収入を得ていたはずであり、その額は日額1万0846円(賃金センサスH28年男子中卒30歳~34歳の平均賃金)×809日=877万4414円であると主張しました。
しかし、裁判所はまず、被害者が新しい不動産会社の経営に参加してより高い収入を得られる証拠はないとして、休業損害算定のための日額は、事故前の収入をもとに日額1万0191円と認定しました。
次に、症状固定までの全期間就労不能であったとはいえないとして、次のとおり段階的に休業日数・休業率を認定しました。つまり入院中の90日間は100%就労不能、退院後の640日間は一定の労務に従事していたとして(その仕事量は従前の20%)この間の休業制限を80%、さらに大腿骨骨折の抜釘手術から2・3ヶ月後には就労が可能で、階段の昇降等には支障があったものの右拇指と鎖骨は日常生活上の問題がなく事務職への従事は可能になっていたとして、症状固定までの79日間は従前の50%の就労制限があったと認定し、次の算式により休業損害を算定しました。
(計算式)
1万0191円×(90日+640日×80%+79日×50%)=653万7526円
②後遺障害逸失利益
被害者は、事故がなければ同僚らと新たな不動産会社を立ち上げてより高い収入を得ていたはずであるとして、412万8200円(賃金センサスH30年男子中卒30歳~34歳の平均賃金)をもとに、67歳まで34年間にわたり20%(後遺障害等級11級の法定労働能力喪失率)の労働能力を喪失したとして、1336万9588円の逸失利益を請求しました。
これに対して、加害者は、事故前の現実収入をもとに逸失利益を算定すべきであるし、被害者の症状は階段昇降時の軽度疼痛等で事務作業であれば支障はないとして労働能力喪失率は14%、さらに症状は将来的に永続する蓋然性はないとして労働能力喪失期間は10年に制限されるべきであると反論しました。
裁判所はまず、被害者が事故前より高収入を得る見込みに関する証拠はないとして被害者主張の年収412万8200円に基づく算定を否定し事故前の現実収入を採用しました。次に、労働能力喪失率は被害者主張どおり20%と認定しましたが、労働能力喪失期間は15年に制限しました。
労働能力喪失期間を15年に制限した理由は、疼痛等の神経症状は年月の経過とともに馴化が生じ代償動作を取得することで労働への支障が軽減するというものでした。
この結果、逸失利益は772万1905円と認定されました。
小林のコメント

本件の判決は、症状固定まで休業を余儀なくされたとする被害者の主張を認めず、在宅で仕事をしていたとする病院のリハビリ記録や症状の回復程度も踏まえ、休業日数(休業率)を100%→80%→50%と段階的に認定しました。
裁判ならではの証拠に基づいた緻密な事実認定と評価手法といえます。
また、逸失利益は通常、症状固定から67歳の就労可能年までの期間にわたり症状が残存することを前提に算定されるので、症状固定時33歳の被害者は67歳までの34年が労働能力喪失期間とされますが、判決では、局部の神経症状に過ぎないこと等を理由に労働能力喪失期間が15年に制限されました。
判断根拠には、局部の神経症状である事等の整形外科的知見もありますが、「後遺障害診断から4年以上が経過した本人尋問時においても改善がみられない様子」であると述べているにもかかわらずこのような認定をした背景には、被害者が身体的な回復力がある若年者であることも影響しているのではないかと思います。
【2025年3月27日更新】
執筆者:渋谷シエル法律事務所 弁護士小林ゆか